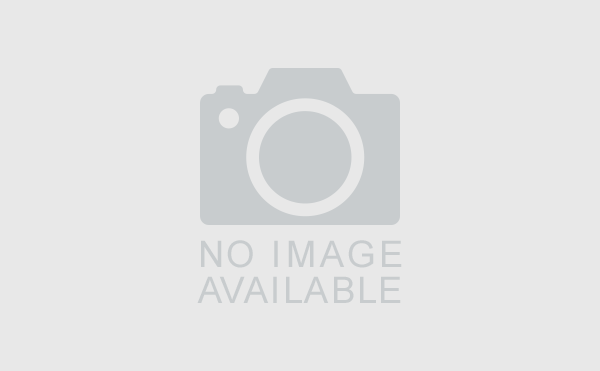『有と無』
2014年刊行の『具体と抽象』がロングセラーとなり、以来、第2弾『無理の構造』(2016年)第3弾『自己矛盾劇場』(2018年)と刊行されてきた、dZEROの細谷功著作シリーズの第4弾が久しぶりに登場した。
『有と無』というタイトルどおり、「有るもの」に着目した思考と「無いもの」に着目した思考に注目して、世の中のさまざまな事象への「ものの見方」を解説する本だ。
「有るもの」と「無いもの」は対称的な二項対立の構図のように思えるが、実はここには非対称性がある。「有るもの」は「無いもの」に比べて圧倒的に少ないのである(「無いもの」が多いというのもおかしな表現だが……)。そして非対称であるにもかかわらず、そう認識できない、という人間の認知の癖が世の中を動かしているーーそんなフレームワークに合う17の例を次々と取り上げていく。
例えば「正解」。世の中にある問題のほとんどには正解がない。にもかかわらず、日本人の大多数を占める「ある型」思考の人は、数少ない「正解がある問題」にばかり着目し、無限に存在する「正解がない問題」に目がいかない。一方で「ない型」思考の起業家やイノベーターは、まず「正解がない問題」に着目し、新たな価値を生み出し、世の中を変えていく、という具合だ。
他に取り上げるのは「自分」と「他人」、「同じ」と「違う」、「カイゼン」と「イノベーション」、「安定」と「変化」など。これらが上記のフレームワークにハマるのはなんとなくわかると思うが、「ツッコミ」と「ボケ」など一見そうは見えないものを、同じフレームワークで語られていくのも面白い。「あれもこの構図に当てはまるかも」などと頭に思い浮かんだことを考えながら読み進めると、非対称なものを対称だと捉えてしまうことで不自由になってしまっていた自分の思考がどんどん解き放たれていく気がする。
AIが劇的に進化しつつある現代は、「具体」より「抽象」、「自分の主観」より「メタ認知」、「経験」より「思考」を重視する「ない型」思考がより重要になるのは言うまでもないことだろう。一方ふだん私が関わっている教育の分野がいまだ「ある型」思考ばかりであることに暗澹たる気持ちにもなる。
この本にもまた「正解」が書かれているわけではない。「答えのある」ところから「答えのないところ」へ向かう、オープンエンドな本なのだ。短時間で読める本だが、読み直すたびに発見があり、問いがどんどん生まれてくる。
例えば私は、何度も読み返し、思考を突き詰めるほどに、「抽象」とは何かが、逆にわからなくなってしまった。本書の原点とも言える同著者の『具体と抽象』を10年ぶりに再読する必要がありそうである。
『有と無』細谷功著 dZERO