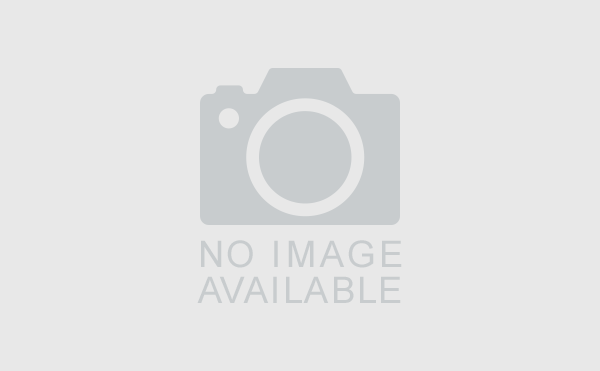『「科学的に正しい」の罠』
「科学の言葉」が、いつのまにか誰かの“物語”を正当化するための道具と化す――本書『「科学的に正しい」の罠』は、その怖さと向き合うための本とも言える。著者は進化生物学者の千葉聡。『歌うカタツムリ』で毎日出版文化賞を受け、『ダーウィンの呪い』は新書大賞10位にランクインされた。読み物としての面白さに加えて「科学の危機」に対する著者の真摯な思いと強い意志が感じられる骨太な一冊だ。
著者はまず、国家やイデオロギーが科学を“都合のよい物語”にしていく過程を描く。ソ連のルイセンコ主義(ミチューリン生物学)は、党の教義に合わせて遺伝学を抑圧し、反対者の解職・投獄を招いた。これは「イデオロギーが科学に枠をはめる」典型として繰り返し参照される。そして現代の事例として、インドのモディ政権で似非科学が跋扈し、科学的な論理が「非愛国的」だと攻撃にさらされている事実を取り上げる。
2020年にリチャード・ドーキンスが「(倫理的問題は別として)技術的には優生学が“機能しうる”」とツイートして炎上した件は、「科学的事実」と「倫理判断」の混同の好例で、事実から“べき”を導けないというヒュームの法則、そして「自然な事実=善いこと」と短絡するムーアの自然主義的誤謬による解説は、まさに正しさに呑まれないための、思考の座標軸として非常に有効だ。
著者は、私たちの日常に潜む“それっぽい科学”を次々に遡上に載せていく。「左利きは9年短命?」「右脳型・左脳型」「カンブリア『爆発』は爆発ではない?」といったトピックが並ぶが、いずれもデータと用語法を吟味すると、レトリックが現実を書き換える仕組みが浮かびあがってくる。実際、左利き短命説は報告バイアスで説明でき、右脳/左脳型の“性格タイプ”も神話に近い。そしてカンブリア“爆発”は地質学的には1300万〜2500万年規模の漸進的多様化にすぎないのだ。科学と似非科学の中間に位置する「ジャンク・サイエンス」もやっかいだ。統計や再現性の粗さを、強いレトリックやイデオロギーで上塗りする説明は、疑似科学と地続きで、時に差別や優生思想の正当化へと誘導する。
そのうえで著者は「罠」はまらないために武器を示してくれる。データの質(設計・統計・再現性)、語り手の立場と利害、用語のフレーミング、相関と因果の取り違え、「価値中立」装いの有無……これらを携えることで、私たちは、「科学的に正しい」と思い込んで信じていることの中に隠れている「誰かにとっての都合のよい物語」を暴くことが可能になるのである。
『「科学的に正しい」の罠』(千葉聡 著/SB新書)