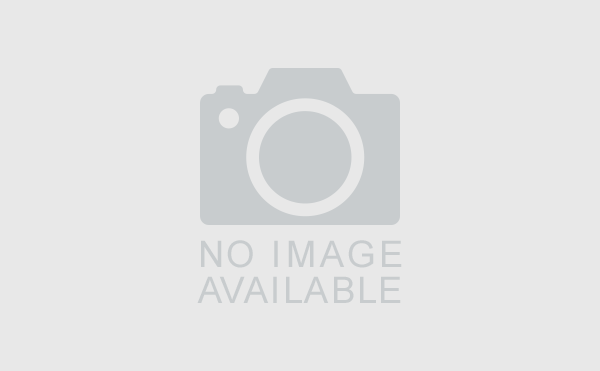第97回 ヒラの記者が副編集長の2倍も稼ぐ、知られちゃいけない出版社の「給料事情」
今回は、読者の皆さまお待ちかね、出版社の「給料事情」を暴露しようと思う。「お待ちかね」じゃないって?(笑)。でも、新入社員の時分には、大学の同級生によく「初任給」のことを聞かれたことを思い出す。
同級生は都市銀行、メーカーといった大手企業にこぞって就職したので、給料のことは概ね知れている。その点、出版社は非上場企業であり(今でこそ、幻冬舎やKADOKAWAといった上場企業はあるけれど)、なんとなく「高給」というイメージがつきまとってはいるものの、その実態はあまり知られていない。
で、新人研修のオリエンテーションで、最初に総務部長に釘を刺されたのは、「同級生と呑んでも、初任給の話はするな」ということだった。
1980年代後半で、確か30万円近かったと思う。三菱銀行とか住友銀行の初任給が15万円とか16万円の時代である(当時の都市銀行など金融機関は、初任給が横並びだった)。言われなくても、これじゃ給料の話はできない。
しかも、筆者が勤めていた出版社の賃金制度は、「究極」の年功序列だった。男性であろうと女性であろうと、記者であろうと経理部員であろうと、年齢が同じであれば給料も全く同じなのである。共産主義だろこれ。
新入社員時代のある日のこと、永田町(国会議員会館)に取材に行ったことがあった。タクシーに乗って、見るともなしに景色を眺めていると、イチョウ並木に見覚えのあるオバハンの顔がある。あれっと思ったら、総務部のオバハンである。勤務時間中だというのに脇目も振らずに銀杏を拾っていた(笑)。
すでに定年間近で、仕事らしい仕事もなかったのだろう。そんなオバハンが、20代の若手記者の3倍くらいの年収を貰っていたのだから、大したものではないか。
若い女性社員のお父さんが、会社に怒鳴り込んできたという逸話もある。娘さんの稼ぎがお父さんより多いので不審に感じたのだ。「おまえら、風俗か? 俺の娘に何をさせてるんだ!」と冗談のようだが本当にあった話である。
初任給が高いだけではない。残業も無制限で付けられる。週刊誌記者の残業って、ハンパじゃないですから。筆者について言えば、20代後半で年収1000万円を突破した。
ところが、労働時間については「三六協定」という労使の取り決めがある。残業時間の上限が定められており、これを超えると労働基準法違反となる。
筆者も三六協定に引っかかった。残業時間なんか気にしていて仕事ができるかっつうの。しかしながら労働組合がうるさいので、面倒臭くなって残業代をつけるのをやめてしまった。文字通りの「ゼロ」である。年収がそれで300万円も減っただろうか。しかし、暮らし向きはかえって楽になった。
というのも、取材費(接待費)を全額請求するようにしたからだ。残業をつけてた頃は、取材費はいっさい請求せず、自腹を切っていた。奇妙な符合ではあるけれど、その当時の残業代と取材費がちょうど同じ300万円くらいだったのである。
で、課税所得が減った分、可処分所得は逆に増えたわけですね。その後、いっさい残業をつけることがなかったおかげで、副編集長に昇格した時も助かった。副編集長には残業手当はつかないので、役職手当(スズメの涙みないな)だけでは減収になってしまう。はなから残業手当がなければ、役職手当(スズメの涙みたいな)の分だけ増収になる計算だ。
ここまで書けば想像がつくかもしれないが、そうなんです。副編集長とヒラ記者の年収逆転とかはフツーに起こるんですよ。ああ、腹立たしい(笑)
まず、年齢がだいぶ上の記者の場合、そもそも年功序列賃金ゆえに追い抜けない。年下の場合も、残業手当に負けてしまう。
副編集長になって間もない頃(30代半ば)、20代の女性記者の給与明細が間違って机の上に置かれていたことがあった。当然のように封筒を破って明細を見ると、手取りがいつもの約2倍に増えている。
なんじゃこりゃ。と考える暇もなく、「それ、私のじゃありません?」と当の女性記者にひったくられた。こちらの給与明細は彼女の机の上に置かれていたらしく、焦って取り返しにきたのである(笑)
仕事ができる記者にとって、それでモチベーションが下がるかと問われれば、全くそんなことはないから、不思議といえば不思議である。
働くことのインセンティブが、「給料」ではなく「やりがい」にあるからだろう。やりがいがなければ、アホらしくてこんな仕事はやっていられない。逆にやりがいがあれば、給料の「不公平」などは気にならないものなのだ。一定水準以上の収入が前提にあればこそ、だが。
閑話休題。
1980年代、出版社で最も高給なのは業界大手の講談社、小学館、集英社ではなく、児童書専門の「福音館書店」だと言われていた。
児童書ってのは、書き手が限られているから編集者は少なくても回るし、子どもがいる限りは読み手も常にいるわけで、つまりは人手も販促費もさほどかからないのですね。絵本のロングセラー『ぐりとぐら』なんかは、放っておいても売れ続ける。
同じような例として、医学系の出版社とか教科書専門の出版社が思い浮かぶ。医学書は単価が高いし、教科書は本屋で売る必要がない(しかも、毎年必ず売れる)。流通経費がほとんどかからないわけだ。
原価といえば「紙」くらいのもので、株式上場もしていないから配当を増やす必要もない。「ヒト」が元手の商売なので、儲けはそっくり社員に還元される。大手出版社に関する限り、そういうわけで総じて給料は高い。
今は、どうなんでしょうね。
出版市場は、1980年代には2兆円を超えていた。それでも、その頃のダイエー(懐かしいでしょ)1社の売上高とほぼ同じだったのだから、産業規模はそもそも大したことはない。
今は、電子書籍が伸びているとはいうものの、紙の本やら雑誌やらは壊滅状態である。市場規模は紙に限れば半減、全体でも1兆5000億円くらいまで落ち込んでいる。
もっとも、電子書籍・雑誌には紙代がかからないし、既存の取次ルートに比べれば流通経費も破格に安い。減収増益傾向にはあるわけで、そうそう大幅に給料が減るということもないように思える。
生まれ変わっても、週刊誌記者になりたいかって? もちろん、お断わりである。倍くらい給料もらわないと、割に合わない。と当時は毛ほども思わなかったのだから、繰り返しになるが不思議といえば不思議なものだ。