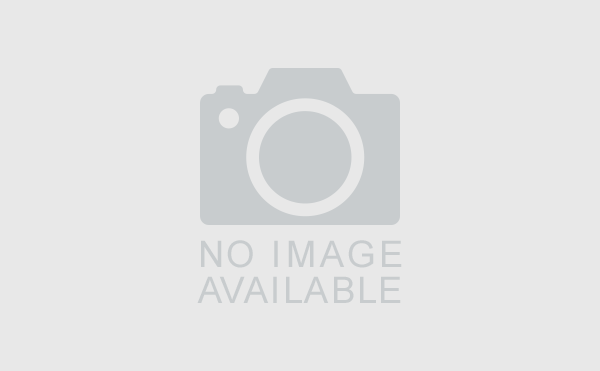『僕たちは言葉についてなにも知らない』
言葉は「魔術」であるーー小野純一の『僕たちは言葉についてなにも知らない』の冒頭にある文章だ。言葉は記号として情報の伝達に使われるだけのものではなく、人やモノにふれることなく、人の感情や行動、ひいては現実そのものを動かす、というのだ。
意味は辞書に固定されているのではなく、話し手と聞き手、状況と文化の相互作用のなかで立ち上がる。小野は意味を「黄身」と「白身」にたとえる。変わりにくい核(黄身)と、文脈に揺らぐ広がり(白身)。私たちの誤解の多くは、この白身の揺らぎを共有できなかったときに生じるが、同時に詩やユーモア、気の利いた言い回しが生まれるのも、この余白があるからだ。たとえば「月がきれいですね」が愛の告白になることもあれば、京都の「ぶぶ漬けでもどうどす?」が婉曲な退出の合図になることもある。
だからこそ本書は、言葉の「黒魔術」への警戒も怠らない。たとえば「誤解させたなら謝ります」という表現――それは非を曖昧化し、責任を相手の理解へと転嫁する。また、トランプ米大統領の発言などを取り上げ、聞き手ごとに異なる含意を狙って仕込む「犬笛」的レトリックが政治や広告でどう機能するかも検討される。言葉の力を自覚するとは、その操作性に無自覚でいないことだ。魔術を使う以上、どちらの魔術をふるうのか――人を欺く黒か、人を支える白か――という倫理が問われている。
興味深いのは、言葉の本質的なあり様そのものが、他者とわかり合えない孤独感を生み出している、という視点だろう。だからこそ、われわれは、言葉にセンシティブであるべきなのだ。言葉の余白に敏感になり、丁寧に扱い、自らの「具体の言葉」へ戻ることが、孤独をこじらせず、自身を他者へとひらく道だ、と本書はそっと教えてくれる。
『僕たちは言葉についてなにも知らない』小野純一著 ニューズピックス刊