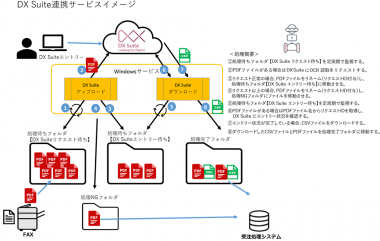第38回 どうしても会いたかった本田宗一郎と色川武大
週刊誌記者時代に、数万人単位の方々と名刺交換をさせていただいた。「インタビューという仕事」についても、すでにこのコラムで紹介しているが、おそらく記事を書いただけでも500人くらいはいるだろう。
話を聞いていて面白いひとは結構いるが、記事を書いていて面白いひとは、なぜかあまりいない。「話し言葉」と「書き言葉」の違いってものがあるんでしょうかね。
「面白い」ということではないが、強く印象に残っているのは、インテルのアンドリュー・グローブCEO(最高経営責任者)、三井住友銀行の西川善文頭取(いずれも肩書は当時)である。
グローブさんには「今日、まだ聞いたことがない質問をしてくれ」と開口一番言われた。来日して、1日に5人も6人もインタビューを受けていたので疲れていたのだろう、と思う。「誇大妄想狂だけが生き残る」という名言を残したように、たぶんにパラノイアの気はあったが、ユーモアのセンスもあって楽しかった。
グローブさんの部下になりたい(もしくは、一緒に働きたい)とは毛頭思わないが、もう一度話を聞いてみたかったとは思う。
西川さんの話は、つい先日の追悼コラムにも書いた。インタビュー中に、あれだけ猛烈に罵倒されたことは、後にも先にもあれ一度きりしかないので、やはり印象に残っている。根は善人なんだろうけれど、部下になりたい(もしくは、一緒に働きたい)とは思わないし、もう一度話を聞いてみたかったとも思わない(笑)。
翡翠職人の口伝が、中国にある。翡翠細工の名人が、弟子入りしたばかりの若者に来る日も来る日も翡翠の珠だけを観察させ続けるというものだ。何年も何年も、弟子はひたすら翡翠を見つめるだけの日々を送る。細工の技などは、全く教えてもらえない。
ある日、師匠たる名人が、いつものように翡翠珠を取り出す。すると、弟子が言うのだ。「お師匠様、これは翡翠ではありません」。贋物を見破った弟子ににっこり笑いかけた師匠は、その日からようやく手技を教えるようになった、というものだ。
いささかニュアンスは違うけれど、インタビューの仕事(というよりも、記者という仕事の本質)も、これに近いものがあるように思う。
技巧などは、やってるうちに身についてくるもので、いちばん大切なのは「人物を見る」ということだ。それこそ何万人というひとと会わなければ、そういう「眼」は得られないものだし、よしんば会ったにせよ、得られるものとも限らない。
というマクラを振って、今回の本題に入ろう。何度も言うけれど、落語では噺に入る前の無駄話(であることが多い)を「マクラ」と呼んでいる。噺のアタマにつくからマクラである。
週刊誌記者をやっていた時代、どうしても会ってみたいひとが2人いた。ホンダの創業者、本田宗一郎と作家の色川武大である。色川という名前を知らなくても、別名の阿佐田哲也はご存じの向きも多いだろう。名作『麻雀放浪記』を世に送り出した、直木賞作家だ。
色川が1989年、本田が1991年の物故である。筆者が週刊誌の仕事を始めたのは1987年だから、ぎりぎり「間に合って」はいた。
しかし、こちとらは駆け出しの身であり、らしくもなく気後れしていた。今ではそんなこともなくなったが、若いころは相手が「巨きい」と、どうしても受け身になってしまう。インタビューの場において、自身の経験・知見不足が露呈するのが嫌でたまらないのだ。
それでも、どうしてもやらなければならない「仕事」であれば、そんなことは言っていられないから、しゃにむに取り組む。この2人の場合、そういう「仕事」がなかったことが、今になっても悔やまれるのだ。
色川は、十代のころから博打に明け暮れ、これ一本で喰ってきたという人物である。余人にはない人生体験から得られた、人間観察と数々のエピソードには、底が知れない深さが感じられる。
同じ作家の吉行淳之介との対談(在りし日の「吉原」について)、落語家の立川談志との対談(「浅草芸人」の思い出について)などを読むと、色川の「人物」がよくわかる。寡言ではあるけれど人間味があって、引き出しが多い。対談相手の本音を引き出し、対談そのものを興味深いものにしている。
余談だが、吉行も「座談・対談の妙手」と呼ばれた人物で、妙手と妙手の対談は一読に値する。機会があれば、是非どうぞ。
こんなおっさんと呑みながら話すことができたらなァ、と思うのである。真面目な話、色川と財界の大物経営者とのシリーズ対談などは、間違いなく面白くて役に立って本になっても読みたいものになったと思う。
そんな企画が実現していたなら、記念すべき第1回の対談相手として、躊躇することなく本田宗一郎にお願いしていただろう。
同時代のアントレプレナーとして、よく松下幸之助と比較される本田だが、これからの日本に求められるのは、松下でなく本田であろうという気がする。
ひと言で言えば、「アニマル・スピリット」だ。オートバイから始まって、自動車産業に参入しようという矢先、当時の通商産業省は本田に「待った」をかけた。怒った本田は、通産省の意向に逆らって、志を貫き通した。その時代の通産省の絶大な権威を考えれば、こんな決断はできるものではない。
起業のアイディアももちろん重要だし、MBA(経営学修士)のような知識も必要だろう。だが、今もっとも問われているのは、この「突破力」ではないだろうか。
夢を実現するために、俺は俺のやれることを全力でやる、という本田に数多の部下が惚れ込み、世界のホンダを共に築き上げていった。そんな人物、ストーリーに、たまらなく惹かれるのである。
こんなことを書いていくとキリがないので、最後に本田の本(というのも、なんだか変な表現になってしまうが)を紹介したい。
『俺の考え』(新潮文庫)。中身についてここでは詳しく触れないが、要するに本田宗一郎の経営哲学を綴ったものである。本田宗一郎という人物のエッセンスが、「俺の考え」という4文字に凝縮されている。
まず、「私」でなく「俺」である。まるで、気取りがない、構えない、ポーズを取らない。ありのままの自分をさらけだす、という姿勢である。良し悪しの問題ではなく、松下幸之助ならここは間違いなく「私」だろう。
そして、「考え」。本田は(松下のように)哲学など語りたくはないのである。おそらくは、この本も、編集者に口説き落とされたものであろうし、本田自身が嬉々として乗ったものだとは思えない。したがって、「哲学」でなく「考え」なのである。「私の哲学」でなく「俺の考え」。実に、なんとも、よいタイトルじゃありませんか。
色川と本田の対談、実現させたかったなァ。対談の後には、3人で酒を酌み交わし、いろいろなお話を伺いたかった。大仰に聞こえるかもしれないが、それだけが今でも心残りなのである。