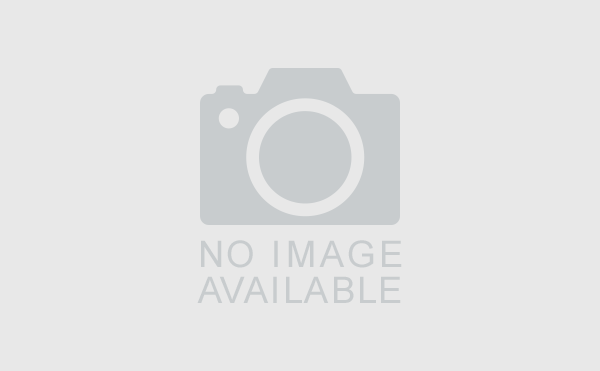第96回 あってはならない「原稿を落とす」、知られざる週刊誌の緊迫締切事情
先月は、いろいろ理由(ワケ)があって、原稿を締切に間に合わせることができなかった。マスコミ業界では、これを「原稿を落とす」とか「原稿が落ちる」とか呼んでいる。
Googleで「原稿を落とす」を検索すると、AIによる概要には”「原稿を落とす」ことは、プロの執筆者にとって自身の信用を落とす行為であり、本来は絶対にしてはならないことです。”とある。改めて、面目ない。と深く頭を垂れる次第です。
実は、この連載では以前にも一度、原稿が落ちている。このときは、締切には間に合っていたのだが、書いた原稿の内容に差し障りがあって「お蔵入り」になった。「代原」(代わりの原稿)を書こうと思えば書けないこともなかったのだけれど、編集者の方で「そこまですることもないでしょう」と助け舟を出してくれた。
どうやら、そもそも、あまり期待されていないらしい(笑)
現役の週刊誌記者時代に、原稿を落としたことは一度もない。付け加えるならば、編集部の記者が原稿を落としたことも、少なくとも23年間の記者生活の中では一度もなかった。
急病にかかったとか、両親が亡くなったとか、締切に間に合わない事情はいくらでもありそうなものだが、なぜか落ちないものなのですね。
もっとも、締切に間に合いそうにないので、「代打」「代原」を予め頼んでおく。ということは、いくらでもある(筆者はやったことはないが)。週刊誌なので、次の号(言い換えれば、締切の1週間前)あたりまでは、それで間に合う。
一度だけ、どえらい窮地に陥ったことがあった。週刊誌の看板である特集記事を担当していた記者が「交通事故に遭った」とかで、締切まで残り1週間を切っているという土壇場で、「バックレた」のである。
「バックレた」とは言い方が悪いが、当時の編集部内では誰もが等しくそう思っていた。交通事故ってあんた、どんな事故に遭って、どこに入院してますのん? 締切には間に合うんかいな? みたいな連絡が一切つかなかったのだ(そもそも本当に交通事故に遭ったのか、後になっても真相は判明しなかった)。
20ページ近い冒頭記事を「白紙」にはできない。副編集長だけ3~4人が集まって企画を立て、取材し、新しい特集をでっち上げて、3~4日で1本こしらえた。そういうわけで、こんな危機にあっても原稿は落ちなかった。
しかしながら、3~4日という急ごしらえで読者に満足していただける特集ができるわけはない。このときの「でっち上げ」には、筆者も関わっていたのだが、何をやったのか全く覚えていないし、思い出したくもない。
「原稿を落とす」で苦労するのは、主として漫画家や小説家の編集者である。漫画家、小説家には「落とす常習犯」がいるので、必ず代原が用意されている。
だが、用意されていると知れれば、漫画家も小説家も平気の平左でバックレるので、編集者は「代原はありません。落ちれば、白紙です」とギリギリまで脅し続ける。それでもなお、落ちるときには落ちる。
ビジネス週刊誌の場合も、「原稿を落とす」で警戒すべきは、記者ではなく外部執筆者だ。ただし、外部執筆者の多くは経営者、大学教授、弁護士・公認会計士等々なので、漫画家や小説家に比べれば社会常識もあり、こちらもまず落ちる懸念はない。
オリジナルな創作で勝負する漫画家、小説家と違って、ビジネス週刊誌における外部執筆者の記事は「知見」を披露するものなので、「脳みそが汗をかくほど考え抜いてもアイディアが出てこない」ということもないから、まァ当然と言えば当然である。
兎にも角にも、人並みに反省はしているので、今回の原稿は早めに出そうと考えていた。締切は「8月31日」と指示されていたが、送稿したのは「8月31日」当日だった。危ういところである。この連載にも「代原」を用意しておいた方がいいかもしれない。
蛇足:
締切が「8月31日」である。掲載日は知らされていないが、掲載日と締切のギャップが、すなわち編集者が読んでいる「サバ」」となる。執筆者に対して、予め締切のサバを読むことは、この世界の常識であって、掛け値なしの期限を教えていたのでは、身体がいくらあっても保たない。