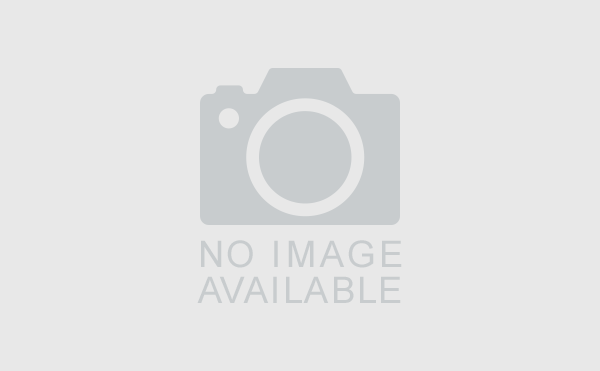第142回 記憶をめぐる冒険
長い間、「中年」を自認してきたが、気がつくともう「初老」である。
それできょうから「初老探偵団」とコラム名を変更します。
という話ではなく、年齢相応に気力体力が衰えてきたという寂しいお話です。
特に記憶力の衰えは凄まじく、目を見張るものがあります(いや、目はもっと衰えているのだが)。
誰もが年齢を重ねるうちに人の名前が思い出せないという経験をしてると思う(若い人でも油断できない)。
私もテレビで見かける人の名前はもちろん思い出せないし、いっしょに仕事をしている人の名前もしばしば忘れる。
つい先日など、役所で手続きをしているときに自分の名前が思い出せなくなった(よくあることだ)。
それはさておき、7月の初めに東北に行ってきた。
その時のことを記憶を辿りながら報告してみたいと思う。
7月2日に北海道苫小牧市のフェリーターミナルから秋田港に向けてフェリーに乗った。
フェリーは多少揺れたが、いつもより多めに摂取したアルコールのおかげで船酔いを防ぐことができた。
翌朝、二日酔いで秋田港に降り立った。そして熱い潮風に吹かれながら駅に向かった(駅名は忘れた)。
駅に何をしに行ったのかは思い出せないが、駅のそば屋さんで卵とかき揚げの入った暖かいそばを食べた(美味しかったが、冷やしたぬきのほうが良かったなという記憶)。
通勤電車を見送ったあと、車で男鹿半島に向かった。
本当は青森に向かおうとしていたのだが、レンタカーのカーナビの使い方がわからなくて、最初に目に付いた道路案内に従うことにしたのだ。
(脳内地図では男鹿半島経由で青森に行けるようになっていた)
北上していくと、ところどころで赤鬼や青鬼を見かけるようになった。
(赤鬼や青鬼のような絵やオブジェを見かけたと言ったほうが正しい)
どうやらこの鬼は「ナマハゲ」のようだ。
ナマハゲというと、藁の簔を着て大きな包丁を持って「泣ぐ子はいねがー」と言いながら小さな子供にトラウマを植え付ける鬼というイメージだが、この男鹿に住んでいるらしい。
せっかく男鹿に来たので、道の駅に寄ってみた。
海の近くのその道の駅は「オガール」という名前だったと記憶する。
そして道の駅の駐車場の端のほうには4階建てくらいの展望台があった。
名前は「アガール」だった(上にあがるから?)。
道の駅の中の店舗では、新鮮な魚貝類のほか、ナマハゲ図柄のTシャツや本格的なナマハゲのお面も売っていた。
ナマハゲのお面に強く心を引かれたが、深夜の書斎で一人でナマハゲのお面をしている自分を想像して、今回は購入を諦めた。
店舗の外では、パラソルの下で女性がアイスを売っていた。
「秋田名物 ババヘラアイス」
たしかに女性はヘラを持っていたが、ババは失礼じゃないかと思った(棒読み)。
道案内をたよりに進んで行くと、ますますナマハゲとの遭遇機会は増えていく。
橋の欄干にもトンネルの入り口にも当然のようにナマハゲが居る。
そして気がつくと山奥の「なまはげ館」の駐車場に着いていた。
観光バスが並んでいるところを見ると人気スポットらしい。
入場料を払って、なまはげ館に入る。
ナマハゲの歴史が説明されていたり、ナマハゲと写真が撮れる場所があったり、ナマハゲの面を彫っている職人さんがいたりとナマハゲのすべてがそこにあった。
たぶん世界でもトップ3に入るナマハゲ施設と言えるだろう(ほかにこんな施設があるかは知らんけど)。
そして、奥へと進むと、ナマハゲの団体(?)が直立不動で闖入者をにらみつけているのだった。

恐いというか、面白いというか、なんなんだコレは?って感じになる。
それにしても、他に人はいない。観光バスに乗ってきた人達はどこにいるのだろう。。。
と、なまはげ館の裏手に出てみたら、多くの人がたむろしていた。
そこには伝承館という別な建物があって、ナマハゲの実演(!)が見られるらしい。
人数制限があるので、みんな待機中のようだ。
ここまで来て、実演を見ないという選択肢はないので、団体さんに混じって待機することにした。
伝承館に入ると、どこか懐かしい田舎の板の間の部屋があった。
そこにみんなで座って、ナマハゲの登場の待つのだ。
伝承館の案内人に現地の習わしや言い伝えを聞いて、しばらくすると、
ウォー、ウォーという大声とドンドンと床を打ち付けるような大きな足音がして、ザザッと襖を開いてナマハゲが登場した。
おばさんたちの小さな悲鳴があがる。
「ウォー、ウォー、なまけものはいねがー」
平日のまっ昼間にこんなところでナマハゲを見ている全員がなまけものであるといったことはおいといて、しばしナマハゲパフォーマンスを堪能する。
設定としては、大晦日の夜。
ナマハゲは各家庭の家族構成や米の取れ高などの機微な情報を調べ上げていて、大福帳のような冊子を開いて、家の主人に質問をする。
「今年の取れ高はどうだった?」「息子はちゃんと勉強してるか?」「嫁はしっかり働いてるか?」といったような内容で、主人がウソをつこうものなら語気を荒らげる。
そこで主人は一生懸命ナマハゲにお酒を勧める。
ナマハゲは勧められた酒を呑みつつ、「なんか隠してるベ」と主人を疑い、ついにはドーンと立ち上がって「嫁はどごだー、息子はどごだー」と家中を探し歩く(見物客の中に分け入る)。
もし、自分がどこかに隠れてる立場ならちょっと恐いかも。
そんなナマハゲを主人は取りなしながら、「まあまあ」と酒を勧め、料理を勧め、最終的には「来年もよろしくお願いします」といってナマハゲにお引き取り願う。
これがこの地方の風習らしいが、都会ならばこんな風体の人が「なまけものはいねがー」と家に押し入って、「今年の年収はいぐらだった」と聞く前に通報されることだろう。
てなことを考えながら男鹿をあとにする。
青森に向かうには八郎潟を越えねばならず、海沿いにずーっと遠回りしているうち岬に外れに着いた。
「ごらん、あれが竜飛岬」でお馴染みの龍飛崎だ。
ずいぶん早く着いたのは、旅の記憶が薄れているからだろう。
龍飛崎では青函トンネル記念館を訪ねた。
そこではケーブルカーで海底の工事現場へ行くことができる。
なかなかできる体験ではないので、1200円でケーブルカーに乗ることにする。
乗車券を買うつもりで、施設の中に進むと券売所には温厚そうなオバさんがいて、入館料は大人1枚600円だという。
あれ?と思って、周りを見回すとそこは五所川原市の「斜陽館」だった。
どうしてここにいるのか、途中の記憶ははっきりしない。
「斜陽館」は太宰治の生家である。
大地主だった太宰の父が建てたその家は旅館のように大きく庭も立派だ(のちに旅館としても利用されている)。
ここで太宰が幼少期を過ごしたと考えると感慨深い、などと考えながらその一室を覗くと人が入れるような大きな段ボール箱が置いてある。
その横には映画「箱男」で使用されました、と書いてある。
あれ?と思って、周りを見回すとそこは北海道文学館の「安部公房展」だった。
その箱をかぶって「箱男」になって写真撮影してもらえるらしい。
段ボール箱をかぶりたいなんて人はいるのだろうか。
もはや人間として失格のような気がする。。。
と、ここまで書いてから、気になって手許のスマホを開いてみた。
箱をかぶった自分の写真が保存されていた。
「人間の記憶なんて当てにならないのだよ、明智君」(なんのこっちゃ)