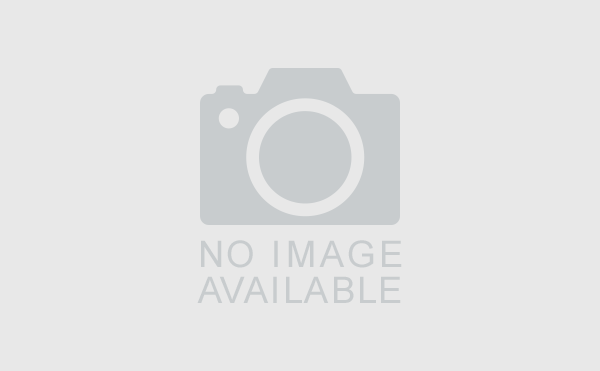第72回 落語で思い出した「社食」の記憶、「通勤手当」で一夜の豪遊を楽しんだあの頃
最近、柳家喬太郎の「社食の恩返し」という落語を聴く機会があった。「社員食堂」という言葉には妙に懐かしい響きがある。
その昔に勤めていた出版社にも「社食」があったせいかもしれない。従業員はたかだか200人くらいしかいないのに、10階建ての自社ビルを保有していて、社食はその地下1階にあった。
エレベーターを降りると、たちまちムッとした臭気が漂ってくる。地下にあるので、胃もたれするような揚げ油の臭いがそこかしこにくっついて離れないのだ。
入社して数ヶ月もたたないうちに、敬わずして遠ざけることになったのは当然の成り行きである。臭いし不味いし、日中は取材(もしくはサボり)でほっつき歩いているしで、そもそも社食になんぞ寄り付かなくなってしまう。
そういうわけだから、メニューなんか全く憶えていない。カレーライスとか蕎麦、うどん、ラーメン程度のものだったのではないか。なにしろ油の臭いがきつかったから、フライや天ぷらの定食なんかもあったかもしれないな。
給与明細には「昼食手当」という項目があって、毎月3000円分の食券が同封されていた。「昼食手当」というくらいだから、社食は昼しか開いていなかった。
100円の食券が10枚ずつ、3つの束になっていて、代金分だけ切り取って使う。お釣りはどうしてたんでしょうかね。仮にカレーライス350円なら、食券4枚出して50円お釣りをもらったはずだが、そんな記憶もない。
手つかずの食券は、年の暮れに物販(主として食品)で使うという手があった。会社がカタログを配り、業者がやってきて、社食で陳列販売する。1年分なら3万6000円になるから、そうとうな使い出があり、ちょいと値が張る「カニ缶」が一番人気だった。
他には、社内に「ブローカー」(年かさの女性社員)がいて、食券を買い取ってくれる。よくしたもので、経理・総務といった内勤社員にとっては、安い社食でも月3000円では足りない。売る者あれば買う者ありで、絶妙の需給バランスが成り立っていた。
食券の買い取り価格は通常は「1割落ち」である。「ブローカー」は2700円で買い取り、たぶん2800円とか2900円で売っていたのだろう。定価では売れないだろうし2700円では手間賃にもならない。
どうかすると、2年くらいたまってしまうこともある。ブローカーに持ち込むと「大量買い取りは2割落ち」ということで、2400円に買い叩かれた。2年分ともなると即座には売りさばけないので、リスク分を割り引くのだそうな。これぞ、市場原理である(笑)。
社食で思い出したが、「通勤手当」というのもありましたね。昨今はコロナ禍に伴うテレワーク定着で廃止の機運もあるようだが、これ自体は珍しいものではない。
珍しかったのは、「現金支給」だったということだ。しかも、定期券を買った領収書すら要らないというのだから、渡りに船、濡れ手に粟である。
半年に一度、10万円近いボーナスが入ってくるようなもので、その日のうちに呑み代に消えてしまうのが常だった。
毎朝の通勤には、切符を買う。ところが、これにもカラクリがあって、ほとんど毎日取材に直行するものだから、切符代は取材費で落ちる(妙な話のようだが、実際に落ちていた)。
帰りは、締切で午前様になったり、取材先と呑んでいて遅くなったりして、タクシーを使うことになるが、これまた取材費扱いになる。
つまり、定期券などは初手から必要ないので、通勤手当は丸儲け。食券と併せて年に1~2度は結構な贅沢をさせてもらったものだ。
蛇足を連ねれば、食券と通勤手当は「記者」ならではのフリンジベネフィットではあったが、肝腎の給料には男女・学歴・職種による格差はいっさいなく、驚くべきことに「年齢」だけで決まっていた。
極端なことを言えば、40歳の大卒男性記者と、40歳の中卒女性社員の給料が全く同じなのである(厳密に言えば、残業代等があるので全く同じということにはならないのだが)。
ジェンダー問題では時代の最先端を走っていたということに結果としてはなるにせよ、一般企業で言うならば「総合職」と「一般職」が同じ給料って、あり得なくね?
定年になるまで給料は上がり続ける仕組みになっていたので、筆者の「倍」近い年収をもらっている女性社員はザラにいた。
あゝ、もう!
余計なことまで思い出してしまった。こんなことを言い始めると止まらなくなってしまうので、今回はここで筆を擱くことにしよう。
損保問題の続きを書く予定になっていたことは、もちろん忘れてはいない(本当です)。次回をお楽しみに。